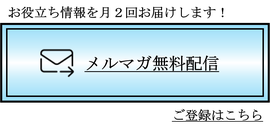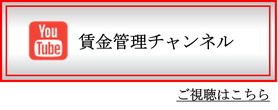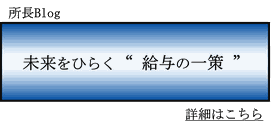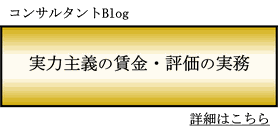企業の成長は、制度や戦略だけでなく「人を育てる姿勢」によって決まります。特に中小企業では、管理職の力量が現場の空気をつくり、組織の方向性を左右します。だからこそ、まず管理職の育成にとりくむことが経営の根幹であり、単なる人事施策にとどまらず、企業文化そのものに関わるテーマだということができます。
その育成の起点となるのが「評価制度」です。評価制度は、処遇を決めるための仕組みというだけではなく、管理職一人ひとりが「自分に何が期待されているか」を理解し、成長の方向性を掴むための重要なツールです。制度の設計と運用に、経営者の育成への理念が込められているかどうか。それが、組織の成熟度を映し出します。
しかし実際の現場では、「能力があるかどうか」を漠然と評価しがちですし、そうした能力基準を前面に出した「人事考課制度」も広く使われているのが実情です。結果として、ハロー効果(印象による評価の偏り)により、「できる人はどの項目でも高評価」「一度つまずいた人は全てにわたり低評価」といった不公平が生まれやすくなります。これでは育成の機会が失われ、組織の健全な成長が阻害されてしまいます。
そこで重要なのは、「職責の遂行度」を評価の中心に据えることです。特に課長クラスに対しては、どのような役割を期待しているのかを明文化し、それに対してどの程度、職制上の責任を果たしたかを相対比較を交えて評価する。たとえば、「部下の育成」「業務の改善提案」「他部署との連携」など、具体的な役割に対して行動や成果をもとに評価する仕組みを整えることで、評価は評価者の主観をはなれ、職務遂行の実態に基づいたものになります。
また、評価項目は「〇〇力」といった抽象的な能力表現ではなく、「〇〇の責任を果たしたか」「〇〇の行動を取ったか」といった着眼点に落とし込むことが肝要です。これにより評価者の視点が統一され、被評価者にとっても「何をすればよいか」が明確になります。
運用面では、管理職を評価する立場にある部長以上の経営幹部が、日常的に管理職の行動を観察・記録できる仕組みが不可欠です。会議録や週報、面談記録、更には1on1の記録なども活用し、評価時に「何を根拠に判断するか」が明示されることで評価全体への納得感が高まります。さらに、評価結果は育成面談に活用され、「次にどこを改善するか」「どのような行動を増やすか」といった具体的なフィードバックにつながれば、管理職の成長が促されることになります。
評価制度は育成の器であり、経営者の人事哲学を映す鏡なのです。制度の整備と運用の工夫を通じて管理職が自らの役割を理解し、主体的に成長していく土壌をつくること。それこそが、「人を育てる会社」としての第一歩となるのです。